渋谷区で主として中古マンションの売買仲介を行なっている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。
2023年10月5日のブログ「水道料金は今後上昇していきます!」で水道料金の値上げが始まったことをお伝えしましたが、遂に全国的な水道料金と下水道料金の値上げが本格的に始まっています。
2024年の引き上げは神奈川県など全国で上水道で100、下水道74の延べ174の自治体にのぼっており、前年度の128の自治体の値上げを36%上回る状況となっています。
今回値上げした自治体の数は、消費税が5%から8%になり値上げが相次いだ2014年度の延べ210の自治体に次ぐ多さとなっています。
人口減少に伴う収入減と物価高により水道事業並びに下水道事業の大半は赤字となっており、財源不足で老朽施設の改修も追いついていません。
更に、2025年1月28日に発生した埼玉県八潮市での下水管の損傷による道路陥没事故が発生したことを受け、国土交通省が2月22日に初会合を開いた有識者委員会では、直径2m以上の比較的大きな下水管は全国に約9,700kmあり、20年後には全体の約6割が耐用年数を超過するとの試算が示されました。
国は自治体に腐食しやすい構造の下水管については5年に1回以上の点検を義務付けていますが、それが適切に行われていなかった可能性もあり、いずれにしろ点検にかかる費用も増大するのは確実です。
今回の道路陥没事故では、周辺住民だけでなく、近隣の市も巻き込まれ、周辺自治体に暮らす住民も含め約120万人が下水の利用自粛を求められており、大規模な自然災害に匹敵するような重大な事態となっています。
高度経済成長期に整備されたインフラは老朽化が進んでおり、今回の事故は2012年12月に起きた笹子トンネル天井板落下で走行中の車3台が下敷きになり9名の方が亡くなった事故と同様に、整備点検のずさんさが招いた可能性も否定できず、実際に事故が起こらないと対策を施さないという自治体の実態が今回も浮き彫りになった形となっています。
民間の研究グループ(EY新日本有限責任監査法人)の公表によると、水道の経営安定には対2021年比で2046年度までに、全国平均で約48%の値上げが必要とし、人口が密集しており経営が安定しているとされてきた東京都でも25%の値上げが必要としています。
上記試算から考えると、この八潮市で起きた事故により、更なる調査費用や点検回数の見直しは確実に増加するため、今後点検費用なども含めた分の上乗せ値上げは必至であり、現状の値上げ幅を見ると既に値上げした自治体も含め、トータルで更に2割から5割も上下水道の料金が上昇する可能性があります。
これから不動産購入をされるエリアの水道料金や下水道料金がどれくらいかは、下記「生活ガイド.com」サイトにより確認が可能です。
https://www.seikatsu-guide.com/ (生活ガイド.comサイト)

水道と下水道の料金の仕組み
一般家庭が支払っている水道代は、上水道料金と下水道料金を合計した金額です。
上下水道は各地の自治体や複数の市町村でつくる一部事務組合という行政機関が運営しています。
上水道と下水道それぞれの使用水量などに応じた利用料金を設定し、一般家庭に請求を行っています。
上水の場合は、利用料が増えれば、料金もあがりますが、下水道の料金はどうなっているのでしょうか。
トイレや洗濯、料理などで使用した生活排水は多くの不純物が含まれており、そのまま川などに流すことはできないため、浄化をする必要があり、この浄化の役割を担っているのが下水道です。
生活排水を浄化するには処理する施設が必要でコストがかかるので、水道を使用する家庭では上水道料金に加えて、下水道料金も負担するケースが多くなっています。
なぜ下水道料金を負担するケースが多いと記載したのかと言うと、下水道が整備されていない場所では料金がかからないからです。
多くの都市では下水道の普及率が90%を超えていますが、普及率が50%以下の都道府県もいくつかあります。
下水道が備わっていない地域では「浄化槽」と呼ばれる下水道と同じ役割を担っている装置で生活排水を浄化します。
下水道が備わっていない地域の場合、浄化にかかるコストだけでなく設置コストも発生する可能性があります。
場所によってはバキュームカー(衛生車)による汲み取り式が使われているエリアもあります。
また、上水道の料金は、使用した水の量を基準として計算されますが、下水道料金は水の使用量ではなく、下水道に流れた水の量が料金計算の基準となっています。
このような違いにより、上水道と下水道の料金に差が生じるケースがあり、また、下水道は利用していなくても最低基本料金が設定されている場合もあります。
また、下水道料金の基本的な考え方として、下水道料金は下水道を利用している地域の住民全体で負担をするといった考えが前提にあるために、住民数が少ない地域に関しては下水道料金が住民数が多い地域と比較して割高になっている可能背があります。
そのため、住民数が多い自治体や生活用水の貯水池が存在している自治体は下水道料金が比較的安い傾向にあります。
水道料金と聞くと「上水道の使用料金」をイメージしがちですが、一般的な水道料金には下水道の料金も含まれており、自治体によって料金計算の仕組みが異なりますので心にとめておきましょう。
上下水道の職員削減は安全性を損ねる
水道事業では浄水場や配水管、下水道事業も生活排水の浄化には大規模な設備を抱えているため、コスト削減が難しく、むしろ今後の設備の老朽化に伴う点検や更新で費用は増大していくことは必至と思われます。
例えば新潟市では水道職員を2007年以降4分の3ほどに減らして効率化を進めてきたが、安定した給水には、今の職員数がギリギリなので、値上げで経営改善を進めるとの考えのようですが、政令指定都市であれば、設備も大規模なため、むしろ今後は人員を増やさないと、維持管理まで手が回らなくなるのではないかと思ってしまいます。
先述したように高度成長期以降に整備が進んだ水道管は更新時期を迎えており2023年度に法定耐用年数を超えた水道管の割合は5年前より7.5%高い25.4%、下水道管が2.3%高い7.3%となっていますが、2023年度に実際に交換された水道管は0.6%、下水道管は0.2%に留まっており、更新スピードをあげていかないと、上水管の破裂や下水管の損傷による事故が増大していく可能性があります。
上下水道の事業は上水道の6割、下水道の8割が料金収入だけでは、運営費をまかなうことが出来ない採算割れの状況となっており、その不足分は税金や国の補助金で補っている状態となっています。
上下水道事業は、税金に頼らない独立採算性が原則とされており、値上げに踏み切る自治体が増加しています。
このような状況下なので、総務省では2025年度予算案では耐震性の高い水道管に交換する際の自治体への財政支援の拡充を盛り込んでいます。
国の財政はただでさえひっ迫してるので、これ以上の税金投入や補助金による補填は現実的ではないため、今後は更なる上下水道料金の値上げを行う自治体が加速しそうです。
今後の日本の将来のためには、全国でコンパクトシティ化を早急に進める必要があると思います。
『住まいんど診断』であなたの性格に合ったマイホーム探しを始めませんか!
無料で出来る自分自身の性格と住まい探しで重視するポイントがわかる住まい探しのための性格診断ツール
簡単2分で診断完了!まずは公式LINEから診断を!
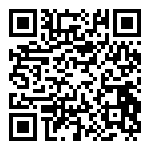





コメントをお書きください